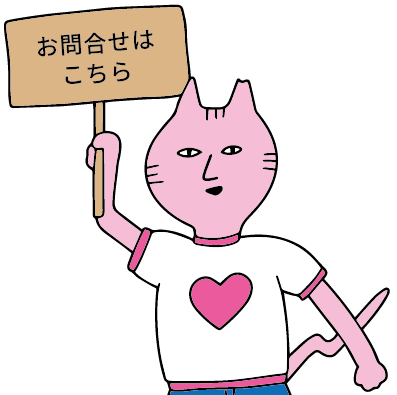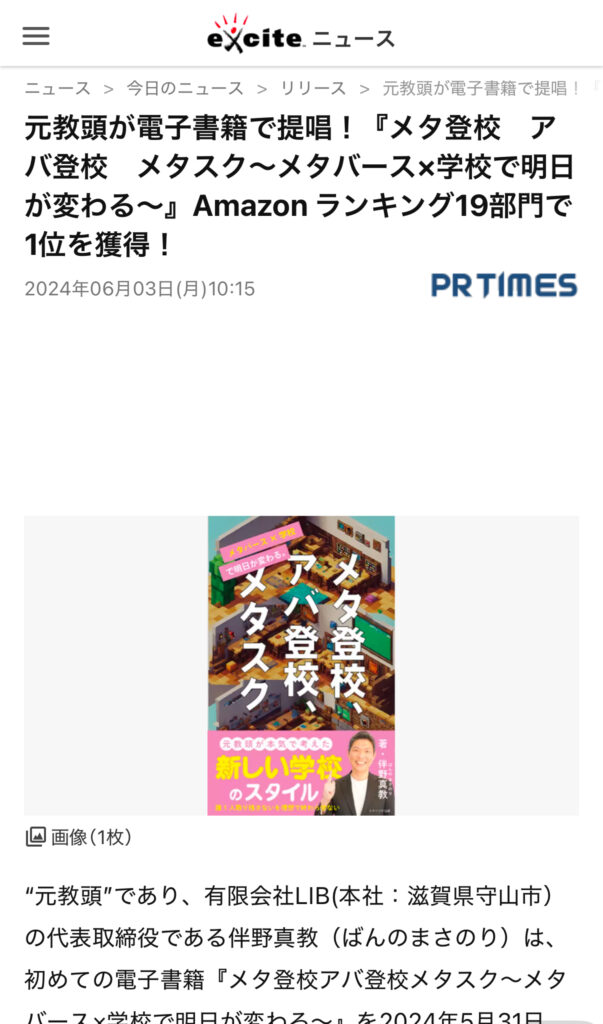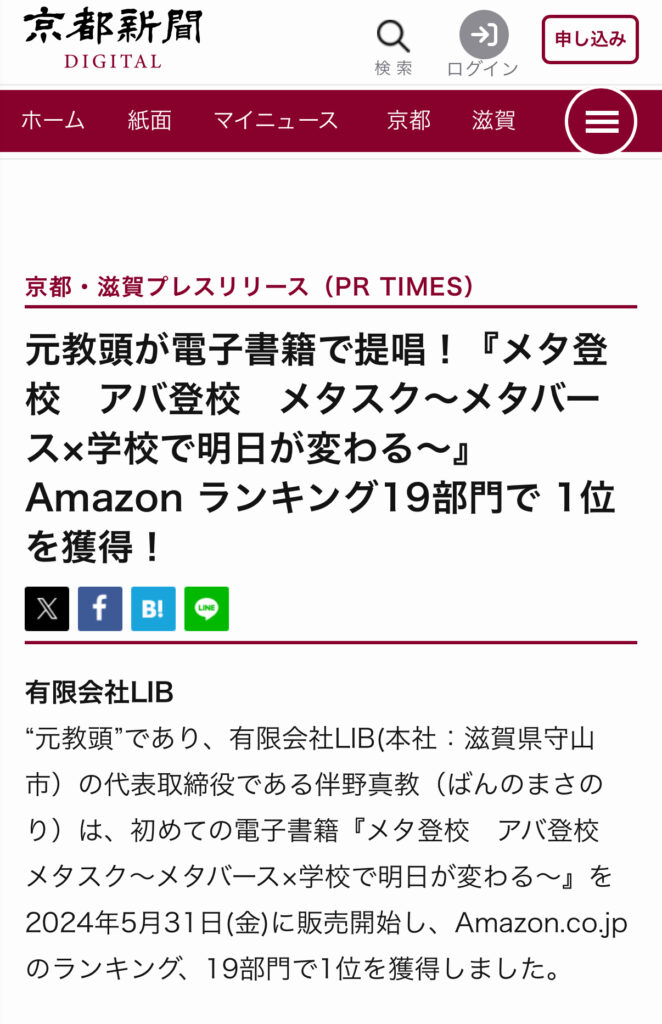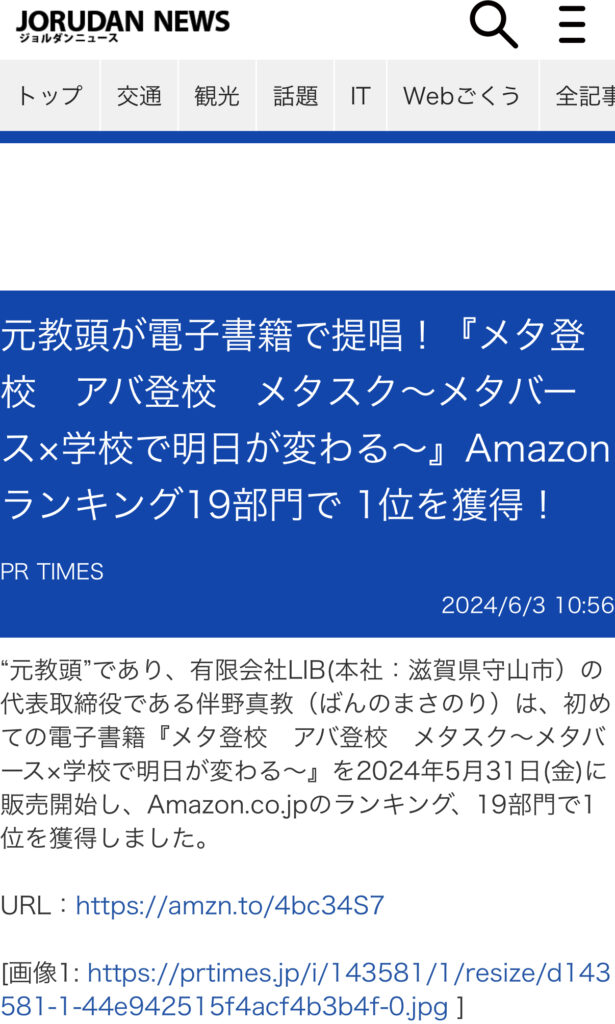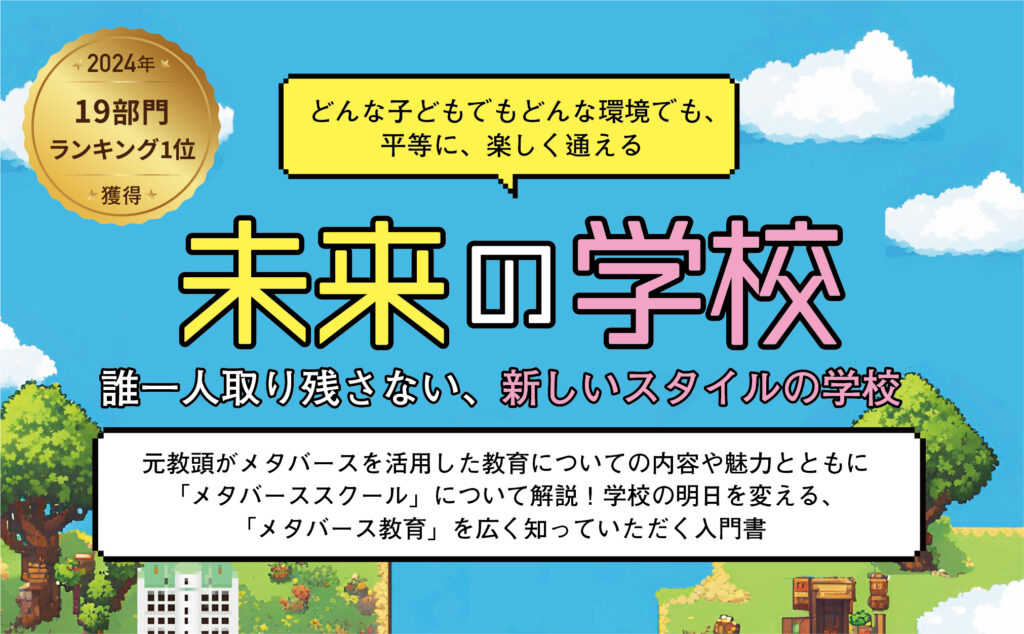
書籍情報

メタ登校、アバ登校、メタスク
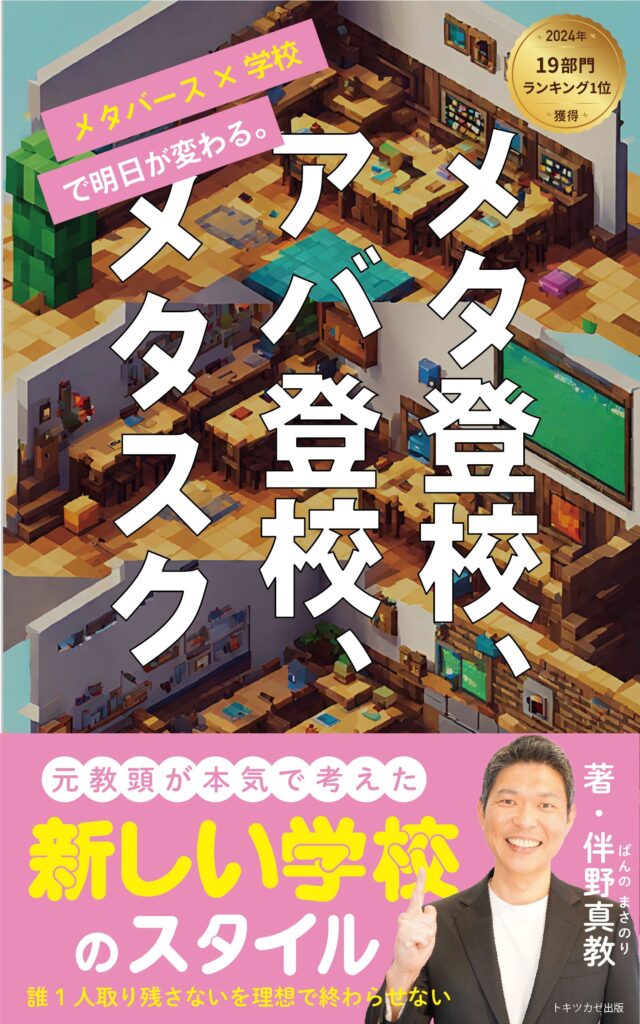
書籍概要
メタ登校?アバ登校??メタスク???
どんな子どもでもどんな環境でも、平等に、楽しく、未来を創れる魔法のキーワード。
世の中では働き方改革が着々と進んでいますが、なかなか変われないのが「学び方」です。今の時代は「学び方」も個性や事情に合わせて多様であるべきですが、相変わらず「横並び」「受け身」の呪縛にとらわれている……。学校の体制や枠に収まりきれない子どもたちは自分の居場所さえ見つけられない現実があります。
世の中の変化に合わせて学校も柔軟に変わっていく必要があると思いませんか?
その解決法の一つとしてメタバースによる授業が注目されています。
メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間のことで、ユーザーは自分の分身であるアバターを使い別のキャラクターとしてそこに存在し、自由に空間内を散策したり、他のユーザーとコミュニケーションを取ったりして楽しむことができます。
メタバースを活用すれば、それぞれの個性や事情に合わせた学びが可能になるはず。
本書では、メタバースを活用した教育についての内容や魅力とともに
私がこれから立ち上げる「メタバーススクール」(通称:メタスク)について解説。
学校の明日を変える、「メタバース教育」を広く知っていただく入門書になればと考えています。
■著者より
私は、大学卒業後、特別支援学校教員、小学校教員として19年、教頭として3年、計22年教育の現場に携わってきました。22年間の教育現場での経験の中で、自分の居場所が見つけられないままの子どもや、メンタル不調から休職、退職する教師を見てきたことから、必ずその子に合った教育の形があり、イキイキとできる場所をつくることができるはずと考え続けてきました。そんな思いを学校や教育委員会にぶつけてきましたが、まさに中央集権的な盤石な組織を変革してくことは困難で、悩んだ結果、退職を決意。本気で教育を変えたいならば、同じ思いを持った方々と、タッグを組んで、それぞれが自律分散型の組織として新しい教育システムをつくり、外から働きかけてみようと思ったのです。そして今、世の中の全ての子どもがワクワクできる「未来の学校」づくりをスタートさせました。
元教頭の経験や視点を活かし、理想とする「誰1人置き去りにしない教育」を実現したい。また多くの方に教育の形は一つではないことを知っていただき、メタバース教育へのご理解を深めてほしい。そんな思いから、この本を出版しました。この本をお子さんに合った個性を伸ばす教育の形を見つけるきっかけにしていただきたいと思います。
これから親になる方、教育の仕事を目指す方、ぜひ一緒に新しい教育の形を私たちと一緒に探り、つくっていっていきませんか?
目次
『はじめに』
第一章 『学校のしんどさの正体』
第二章 『メタバースの学校って?』
第三章 『ハイブリッド型でもっと自由に』
第四章 『子どもがワクワクするミライをつくる学校へ』
『終わりに』
トキツカゼ出版より
長年、教育現場に携わった伴野さんが、「横並び」「受け身」から抜け出せない今の学校教育に疑問を抱き、新たな学びの場としてメタバーススクールをご提案。
メタバースを活用することで、子どもたちは個性や事情に合わせた柔軟な学び方を選択できるようにとの思いで出版されました。
本書では「メタバース×教育」の可能性をわかりやすく解説し、すべての子どもがワクワクしながら学べる未来の学校づくりについてご紹介しています。
「学校の枠を超えた、新しい学びのカタチ」を知りたいすべての方へ読んでいただきたい一冊です。
このようなお悩みはありませんか?

・学校が合わずに不登校になった子に、他の学びの選択肢を探している
・「教室に行けない=学べない」現状に疑問を感じている
・もっと子どもの個性を尊重できる、柔軟な教育方法があればと思っている
・子どもに、社会とのつながりや成長の機会を感じてほしい
・学校の枠にとらわれず、自分らしく学べる環境を子どもに届けたい
・教師の働き方にも限界を感じていて、教育現場を変える仕組みを知りたい
・「メタバース教育って実際どうなのだろう?」と疑問を感じている
・子どもがワクワクしながら学べる、未来に希望が持てる学校があればと願っている
・テクノロジーを活用した学びに関心はあるけれど、どのように始めればいいか分からない
出版後インタビュー

対談内容
中島琴美(以下、中島):
皆さんこんにちは!
今日は、著者の伴野正教(ばんの・まさのり)さんにお越しいただいています。
著書『メタ投稿・アバ投稿・メタスク』は、なんとAmazonランキングで19部門1位!
IT・教育関連の各部門でも注目されていて、メディアでも取り上げられている話題の本です!
伴野さん、もともと教員(教頭)をされていて、合計で22年のキャリアがあるんですよね。
そこから独立されて、不登校の子どもたちの居場所を作る教育へとシフトされたと。
今日は、話題のメタバース教育について、分かりやすく教えていただければと思います!
伴野正教さん(以下、伴野):
はい、よろしくお願いします。
メタバースって一言で言っても、いろんな種類があります。
2Dのもの、3Dのもの、VRゴーグルを使ったもの…Appleの「Vision Pro」もその一つですね。
要は、仮想空間にアバターとして入って、動いたり、何かをしたりできるインターネット上のシステムです。
イメージとしては、昔の「ドラクエ」や「マリオ」の世界に入り込むような感じですね。
中島:
なるほど。じゃあそのメタバースを使って、教育を変えていこうというのがこのプロジェクトなんですね?
伴野:
そうです。「アバ投稿」や「メタバリアプレミアム」など、新しい登校スタイルを打ち出していきたいと思っています。
中島:
実際に本を読んだ方の反応はどうでしたか?
伴野:
皆さん、実は共通して「今の学校教育に違和感がある」と感じているということが分かりました。
一斉・一律の教育では、個性を伸ばすのが難しい。
今の教育システムから漏れてしまっている子どもたちもたくさんいます。
中島:
私の時代はクラスに1人くらいだった不登校の子も、今はかなり増えてるんですよね?
伴野:
はい。今は小中学生で約900万人のうち、約30万人、つまり3%が不登校だと言われています。
つまり、どのクラスにも1人か2人はいる計算です。
中島:
「誰1人、置き去りにしない」っていう言葉、すごく響きます。
行けなくなった子たちの気持ちって、すごく複雑ですよね…
伴野:
そうなんです。インクルーシブ教育って言葉はありますが、実際は難しい。
例えば、読み書きが困難な「ディスレクシア」の子に、漢字を何度も書かせるのは酷です。
でも、計算が得意な子にはその才能を伸ばしてあげたいし、絵が得意、音楽が得意な子もいます。
でも今の教育は、全教科を平均的に底上げしようとする。そこに限界を感じています。
中島:
そうですよね。メタバースだったら、アバターで海に行ったり山に登ったりもできるし…
伴野:
そうです!
病気で入院していても、友達と一緒にバーチャルで修学旅行ができる。
誰でも「同じ立場」で経験できるのがメタバースの良さなんです。
中島:
私、自由な校風の学校に行ったことがあるんですけど、そこでも子どもの自殺の問題が深刻だと聞きました…
伴野:
はい。実はあまり知られていないんですが、2022年には小中高生の自殺者が514人、2023年も513人と、ここ数年は500人を超えているんです。
原因としてよく言われるのは「いじめ」ですが、実際のデータでは「学業不振」「家庭の経済的な問題」などが多く、いじめは少数です。
中島:
夢や希望を語れる文化がないっていうのも問題ですよね…
伴野:
そうですね。日本財団の2019年の調査では、「自信がある」と答えた日本の子どもたちは最下位、夢があると答えたのも6割しかいませんでした。
中島:
では最後に、これからやっていきたいビジョンを教えてください!
伴野:
僕が掲げているのは「ハイブリッド教育」です。
メタバースはディズニーランドの「入場ゲート」のようなもので、そこからフリースクールや地元の学校、企業の体験など、いろんな「ドア」に繋がっている。
リアルとバーチャルを繋ぎながら、子どもたちが自分に合った学びを選べるようにしたい。
農業体験や販売体験など、リアルでしかできないことは、地域と連携してやっていきたいと思っています。
中島:
素晴らしいですね!本当に感動しました。
本のリンクやFacebookも貼っておきますので、ぜひアクセスしてみてください。
今日はありがとうございました!